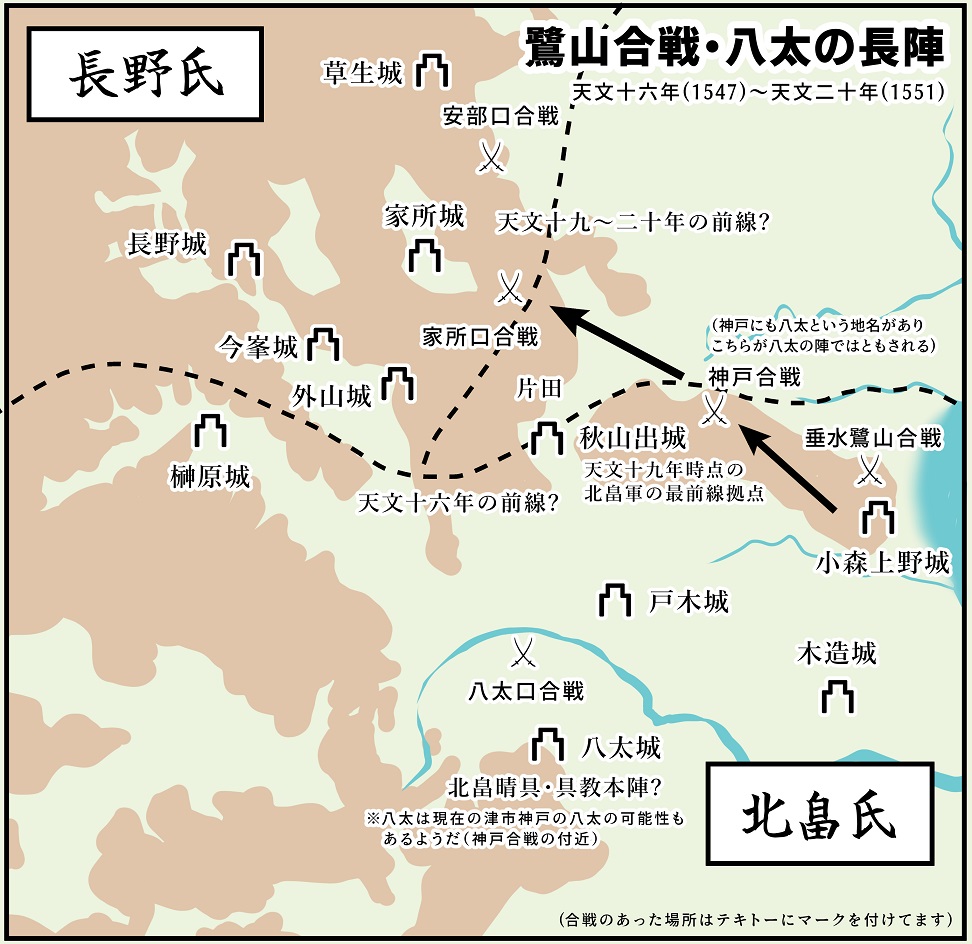戦国大名伊勢北畠氏の歴史 その4 1577~1584
具教粛清後(1577)からの信雄時代です。
これが最終回。
●2月15日 いくつか内容を追加しました。(追加って書いてあります)
その1、その2、その3はこちら
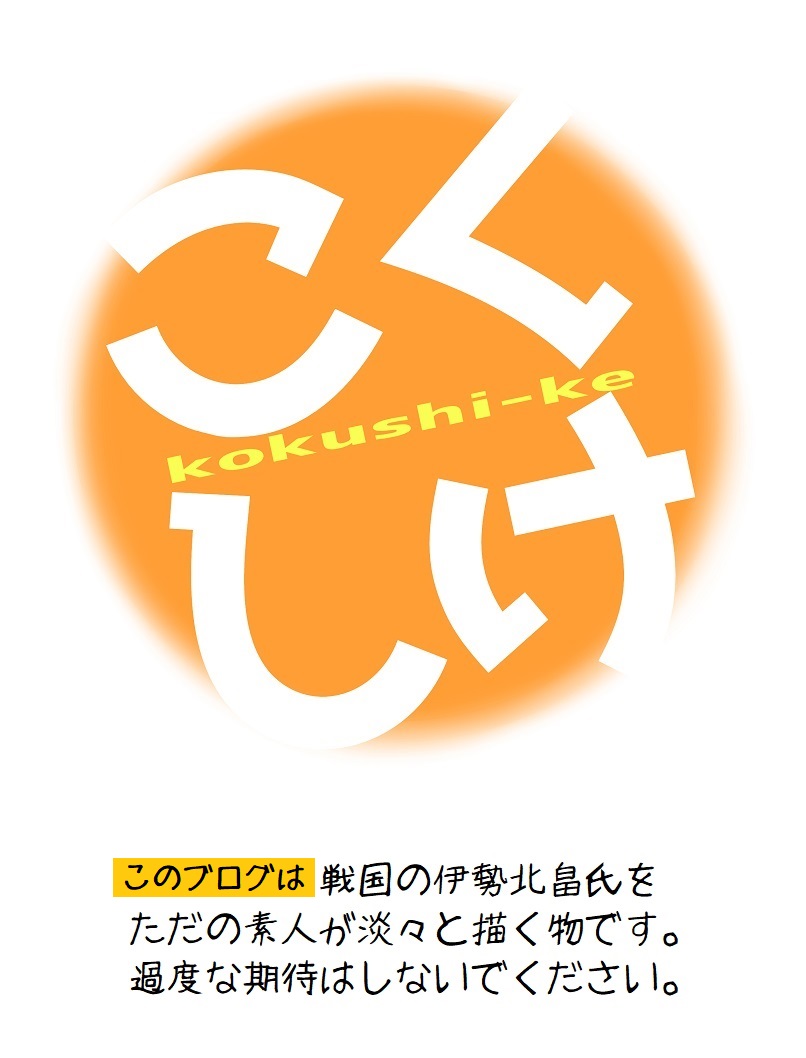

- 1577 雑賀攻め
- 1577 北畠具親の反乱
- 1577 具親、川俣で挙兵する
- 1578 播磨国・摂津国を転戦
- 1579 第一次天正伊賀の乱
- 1579 信長、怒る
- 1579 伊賀攻めの理由
- 1580 信雄、許される
- 1580 居城を松ヶ島城へ移す
- 1581 馬揃えと序列
- 1581 第二次天正伊賀の乱
- 1582 安土への正月出仕
- 1582 甲州征伐
- 1582 本能寺の変
- 1582 北畠信雄と織田諸将の動き
- 1582 伊州蜂起
- 1582 山崎の戦いに参加した北畠旧臣
- 1582 伊賀への対応
- 1582 清須会議
- 1582 名代争い
- 1582 所領分配
- 1582 伊勢・志摩・紀伊の国境変更
- 1582 清須城へ居城を移す
- 1582 信雄の織田復姓と大名北畠氏の消滅
- 1582 信孝と抗争
- 1582 北畠具親の五箇篠山挙兵
- 1584~ その後の織田信雄、北畠具親
1577 雑賀攻め
天正五年(1577)二月、織田軍による紀伊国雑賀攻めが行われ、北畠信雄もこれに参陣しました。信雄は織田氏当主で兄の織田信忠の麾下へ入っています。
三月には雑賀衆の鈴木孫一も城を包囲されてやがて降伏。三月後半には信忠勢も帰陣しているので信雄も南勢に帰国したとみられています。
1577 北畠具親の反乱
天正五年(1577)、北畠具親(東門院殿)が打倒信雄の兵を挙げました。
北畠具親は具教の弟で、出家して孝憲と名乗り興福寺東門院にいたのですが、伊勢から逃れた芝山小次郎たちから国司家一族の粛清を聞いて国司家再興の挙兵を決意。還俗した孝憲は北畠具親(朝親・政親とも)と名乗って伊賀国へ移りました。具親ら反信雄派勢力はどうも伊賀国を拠点にして連携を図っていたようで、これが後々の信雄の伊賀出兵へと繋がったともされています。
具親は粛清から逃れられた坂内亀寿(北畠一族)とも協力します。坂内亀寿については六角承禎も支援を約束していて、承禎は「大本所(六角義治)や将軍義昭に話を通しておく」と伝え、さらに「もし北畠家督を継ぐ者がおらんなら亀寿が継いだらええんちゃう?」と勧めています。具親には子がいなかったので年齢的には幼少の亀寿が適任者だったのでしょう。
翌天正五年(1577)三月六日には亀寿宛に足利義昭の家臣、真木島昭光から書状が届いています。具親と義昭はともに元は興福寺の僧ということで面識があったのではないかとされています。
1577 具親、川俣で挙兵する
兵を挙げた具親、亀寿ら国司家再興軍は伊勢国とへ進出。粟谷・唐櫃・菅野・谷・三田・三竹・小倭郷七人衆らが具親に味方し、さらに鳥屋尾氏、家城氏といった元重臣に峯、森、乙栗栖などが続々とこの挙兵に参じました。伊勢へと入った具親は川俣(香肌峡)の森城へと迎え入れられています。
信雄は滝川雄利、柘植保重、長野左京亮を小倭郷に派遣。さらに森清十郎は三瀬、日置大膳亮は川俣へと向かい具親方を攻撃しました。天正五年(1577)春には具親勢が伊勢国中へと進出しようとしたため、信雄は滝川雄利らも川俣へと向かわせています。戦いは信雄方が優勢に進めたようで、具親に味方した各地の諸家は信雄勢の前に次々と降伏。具親も森城を落とされ、将軍足利義昭を頼るべく毛利氏領国へと落ち延びていきました。
具親に味方した北畠家臣の多くが討死、処刑されたようです。『北畠御所討死法名』では大河内城籠城戦でも活躍した家城主水佑も川俣にて討死となっていて鳥屋尾氏の富永城も落城しました(『勢州軍記』)。
天正五年(1577)八月二十七日に北畠具親が熊野へ立願を行っています。『勢州軍記』の挙兵時期(春)が正しければ立願は挙兵の前ではなく鎮圧後ということになります。さすがに挙兵前が正しいように思いますが……どうなんでしょうね。
九月二日には坂内亀寿が具親と申し合わせて伊賀に逗留中の旨を熊野実宝院へ伝えているので、この時点ではまだ具親も亀寿も伊賀に潜伏していたようです。武田勝頼から激励の書状も坂内亀寿宛に届いています(九月十二日付)。

■ 1578 田丸御局
天正六年(1578)八月、徳川家康が田丸御局宛に「田丸船一艘の諸役を免除するね!」と朱印状を出しました。『愛知県史 資料編織豊1』ではこの田丸御局が北畠具教娘で信雄正妻の千代御前ではないかとされています。ちょうど信雄が播磨方面へ出兵していたので、もしかすると代理で対応していたのかもしれません。
前年に北畠具親の反乱が起こったにも関わらず北畠一族である妻に留守を任せているあたり、信雄からは信頼されていたのではないでしょうか?
彼女は家付娘として信雄を婿に迎えて伊勢国司家当主の正妻となった、信雄の北畠家督という地位を担保する存在でした。信雄も蔑ろには扱わなかったでしょう。たぶん。
(2024年2月15日追加)
1578 播磨国・摂津国を転戦
天正六年(1578)二月、播磨国三木城の別所長治が謀叛を起こしました。信長は信忠の軍勢を摂津、播磨方面へと派遣。北畠氏もこれに従って出陣しています。
なお信雄はこの時期には名前を「信意」から「信直」に改めていたのではないかとみられています(面倒臭いので以降も信雄で書いてきます)。
信忠勢は四月四日から六日まで佐久間信盛勢が包囲していた大坂本願寺を攻撃。五月上旬には播磨へと進み、別所氏方の神吉城、志方城、高砂城を包囲しました。信雄ら北畠勢は志方城を監視する任を受けています。六月下旬には信忠、信孝らの軍勢が神吉城を総攻撃、これを落城させます。信雄のいた志方城へも総攻撃が行われたようですが、こちらは人質を出して降伏しました。三木城へは付城を築いての包囲戦を実施。信雄を含めた信忠勢は八月には帰陣していて、九月九日には信忠や信雄は安土城で相撲を観戦している。兄弟仲がいいね。
十月には大船を率いて大坂へ進出していた北畠配下の九鬼嘉隆が大坂本願寺へ兵糧を運び込もうとした毛利水軍を破っています。
しかし今度は十月に摂津国有岡城の荒木村重が織田氏から離反する重大事件が起こりました。この荒木村重の謀叛鎮圧に信忠軍団が出陣。北畠勢もこれに参加しました。有岡城への包囲が行われますが村重はなかなか降伏せず、翌天正七年(1579)九月に村重が城から逃亡。十一月にようやく城が陥落しました。
信雄ら北畠勢は当初は信忠の麾下にいましたが、有岡城包囲は織田氏の有力部将が輪番で行ったため伊勢に帰国しています。
……そしてまさにその有岡城攻めが大詰めを迎えていた天正七年(1579)九月、北畠信雄は信長には無断で伊賀国へ出兵。惨敗を喫しました。
1579 第一次天正伊賀の乱
天正七年(1579)九月、北畠勢による伊賀侵攻が実施されました。信雄最大のやらかし事案ともいえる「第一次天正伊賀の乱」です。
伊賀国には大名がおらず、永禄年間頃より四郡の諸侍らが相互に盟約を結んで秩序を維持する体制をとっていました。いわゆる「伊賀惣国」です。彼らは他国からの侵攻には惣国が一味同心して防戦すると掟書に記しており、北畠勢の侵攻に対しても惣国を守るべく激しく抵抗しました。
『勢州軍記』では名張郡の下山甲斐守が北畠氏へと味方して伊賀出兵を進言したとされます。九月十七日に北畠勢は一万余の軍勢で場尾口(馬野口?)、名張口から伊賀国へと侵入(『木造記』)。しかし伊賀国は難所であり、地の利を得ない北畠勢は待ち受けていた伊賀惣国一揆の者たちによって散々に打ち負かされてしまいました。
信雄は下山甲斐守に騙されたと怒り、下山を捕らえたうえで伊勢へと撤退。下山はその後、獄中で自害することになります。
名張口からの殿軍を秋山右近将監、沢源六郎らが務め、追撃する伊賀勢と激しく戦いつつも伊勢国への退却に成功。
しかし場尾口では殿軍を担った日置大膳亮、柘植保重が追撃してくる伊賀勢と「両人替々防戦」したが、難所の鬼瘤峠でついに柘植保重が討ち取られてしまいました。
その後、十月三十日に信雄が滝川雄利に書状を出していますが、その内容からするとどうやら滝川は十月になってもまだ伊賀で一揆勢と戦っていたようです。敵地に置き去りにされてる………?
1579 信長、怒る
信雄の無断出兵と大敗に父信長は激怒しました。九月二十二日に叱責状を信雄へと送っています。この叱責状では信雄の伊賀侵攻の理由を「上方への遠征忌避」とみていたようです。そして信長は柘植保重を討死させたことを言語道断と強く非難。信長は「若い茶筅が複雑な北畠家中をまとめていくために柘植保重は必要な家臣」と考えていたようです。
信雄の北畠家督継承からわずか四年。これで信雄は養子入りの際に付随した重臣四人のうち津田一安、沢井吉長、柘植保重の三人を失ってしまいました。以後は残った滝川雄利が北畠家中で中心的な役割を果たしていくことになります。

1579 伊賀攻めの理由
叱責状で信長は「遠隔地への出兵(荒木討伐)を逃れるために近場の伊賀へと侵攻したんだろ!」と怒っています。ただしこれはあくまで信長からみた伊賀出兵の理由であって、北畠側の思惑はそれとはまた別にも存在しました。
先にも書きましたが、北畠具親や坂内亀寿ら反信雄勢力は伊賀に協力者がいて「伊賀を活動の拠点」としていたとみられています。これは信長の命令で遠隔地へ出陣して領国を留守にすることも多い信雄にとっては不安の種です。伊賀を叩いておきたいという考えになるのは当然でした。
信雄は織田一門ではありますが、同時に北畠家督でもあります。信雄は家臣からの支持を得るために北畠領国の安定と秩序を維持しなくてはならない立場なのです。
またそれ以外の経緯として小川新九郎の覚書には「伊賀の領主らが北畠氏より伊勢国内に知行を与えられていたこと」「滝川雄利と柘植保重がその知行を没収するよう信意に献策していたこと」が記されており、この知行没収によって伊賀衆と対立したことも原因の一つであるようです。知行没収がいつなのかは不明。
伊賀攻めに敗れた信雄は当時名乗っていたとされる「信直」から「信勝」へと名前を変えています(天正八年二月までに)。伊賀攻めより前に改名した可能性もありますけどね。なお「信勝」という名前は天正八年七月までに今度は「信雄」へと変更しています。(信長弟で謀叛を起こした織田信勝と同名なことが問題だったのかも?)
1580 信雄、許される
天正八年(1580)。この年は正月十七日に播磨国三木城の別所氏が降伏。四月には長年争った本願寺顕如も大坂本願寺を退去。信長包囲網はほぼ瓦解しつつありました。
五月三日、信雄は兄信忠と安土で屋敷の普請を行っています。前年の伊賀攻めでの失態は父信長からはこの時期までには許されていたようです。
三木城が落ちた後も抵抗を続けていた花隈城も池田恒興らの攻勢によって七月二日にはついに陥落。この花隈攻めに関して九鬼嘉隆が信雄から七月六日付の感状を与えられています。信雄がこの方面の指揮を執っていたらしい。
1580 居城を松ヶ島城へ移す
天正八年(1580)に信雄はそれまで本拠としていた田丸城から参宮道沿いで細汲湊に近い松ヶ島に城を築いて本拠を移しました(『勢州軍記』)。元々は細頸城があった場所とされています。
移転理由を『勢州軍記』では金奉行の玄智という者が金銀を盗もうとした際に田丸城に放火して城が燃えてしまったためとなっています。
しかし天正六年か七年に小川長正へと出された信雄の書状で「田丸城の破却を柘植保重と相談してやってくれ」と命じています。柘植保重は天正七年(1579)九月に伊賀で討死していることから、それ以前には田丸城の破却がすでに始まっていたと考えられています。放火での焼失もあったのかもしれませんが、移転計画そのものは既に決まっていて徐々に進めていたのでしょう。(あるいは当初から松ヶ島に城を築く構想があって、田丸城自体も一時的な本拠だったのかもしれませんね。想像ですが。)
ともかく具体的な経緯はわからないものの、この天正八年(1580)までには松ヶ島城が築かれ北畠氏の本拠が移っています。
現在はわずかに天守台とされる跡が残るだけですが、当時は五層の天守が聳える大きな城郭だったと伝わります。
1581 馬揃えと序列
天正九年(1581)正月十九日、安土城下で馬揃えが行われました。信長はこの馬揃えを気に入ったのか京でも実施しています。
二月二十八日に内裏東側に作られた馬場を織田一門、家臣らがそれぞれ煌びやかな衣装を纏い行進し、正親町天皇や公家衆がこれを見物しました。北畠信雄もこの馬揃えに参加しています。
馬揃えでは当時の織田一門武将らの序列が明確に現れていて、一門の行列順は織田信忠(嫡男)、北畠信雄(次男)、長野信包(弟)、織田信孝(三男)、津田信澄(甥)、織田長益(弟)と続きました。これがそのまま序列と考えられています。
信雄は信忠に続く御連枝衆第二位の位置につけていて、率いた人数は信忠が八十騎、信雄が三十騎、信包、信孝、信澄が十騎となっています。後継者信忠は除くとしても明らかに信雄が他の一門に比べ優遇されています。信忠同母弟、そして北畠家督という立場が信雄の格を高めていたと考えられています。
1581 第二次天正伊賀の乱
天正九年(1581)九月三日、信雄は再び伊賀国へと出陣しました。信雄にとっては汚名返上、名誉挽回のための大戦です。この伊賀出兵は信長の指示の下、織田の戦争として実行に移されています。
甲賀口からは滝川一益、蒲生氏郷、丹羽長秀、京極高次。信楽口からは堀秀政、不破光直。大和口からは筒井順慶。織田氏の有力武将たちが伊賀国へと次々攻め込みます。
信雄は甲賀口からの侵攻で、北畠勢は他にも滝川雄利が別に部隊を率いて加太口から侵攻しました(『信長公記』)。
全方位から圧倒的な兵力で侵攻して来る織田勢に対して伊賀惣国一揆では降伏する者が続出し、抵抗する者も次々と敗れていきました。
織田勢は各郡ごとに担当を決めて一揆の掃討にあたり、山田郡を長野信包、名張郡を丹羽長秀、筒井順慶、蒲生氏郷ら、阿山郡を滝川一益、堀秀政ら、そして阿加郡を北畠勢が担当しました。
いずれの郡も平定されて伊賀国は織田の勢力下となり、名張郡、阿加郡、阿山郡を北畠氏が、山田郡を長野氏が知行することとなりました。北畠信雄にとっては初めての領国拡大です!(加増?)
また以前北畠具親に協力したとされる吉原城主の吉原次郎もこの第二次天正伊賀の乱で討ち取られたようです。ただ後々にも北畠具親らが伊賀へ逃亡しているので、反信雄勢力を完全に押さえ込めたわけでもなかったらしい。全然懲りないな伊賀の連中。
北畠領となった伊賀三郡には滝川雄利、田丸御所(具忠か中務大輔)、木造左衛門佐(長政)、日置大膳亮、藤方御所(具就か具俊)、岡田秀重、津川義冬、池尻平左衛門尉らが配置されています。
(……そういえば木造具政って大河内合戦以降全然名前出てこなくなる気がするけど、もしかして隠居して左衛門佐に家督を譲ってるんだろうか?)
■天正九年からは滝川雄利が伊賀三郡と宇陀郡の支配を担当していたと考えられています。(2024年2月15日追加)
1582 安土への正月出仕
天正十年(1582)正月一日。信雄ら織田一門は安土城へ出仕、正月の挨拶に出向いています。信長はこの出仕の際に全員に百文ずつ持参することを命じていたという。まさかの入城料金。
十五日には左義長(火祭り)、馬場入りも行われました。この馬場入りでは前年の京都馬揃えから序列が変更になっており、信忠、信雄、長益、信包の順になっています。なぜ急に長益(有楽斎)の序列が急に上昇したのかはわからない。なんで?
1582 甲州征伐
天正十年(1582)二月一日、甲斐武田氏に従属する信濃の国衆木曽義昌が織田方へと内通しました。二月三日には信長にも報告が及んだようで武田征伐の実施が下命されます。
駿河方面からは徳川家康が、関東方面からは北条氏政が、飛騨方面からは金森長近が、そして美濃からは織田信忠が侵攻することになりました。勢州四家(滝川一益、織田信孝、長野信兼、北畠信雄)も信忠勢に加わり信濃、甲斐へと出陣。
『勢州軍記』では武田氏が滅亡した田野合戦(いわゆる天目山の戦い)で信雄は相婿である津川義冬を滝川一益勢に加勢させ、津川家臣が土屋源五右衛門尉を討ち取ったとなっています。
武田勝頼は奮戦の末に妻子と共に自害(討死とも)、甲斐武田氏はこれにより滅亡しました。

1582 本能寺の変
天正十年(1582)六月二日、織田信長が明智光秀によって京の本能寺で討たれました。
妙覚寺にいた織田信忠は二条御新造に移って明智勢を迎え撃ちましたが、激しい戦闘の末に敗れ自害しています。
もし信忠が逃げ延びていれば信長の遺志を継いで天下人となり天下一統は織田信忠の手によって成し遂げられたはずです。そうなれば秀吉が天下人になることもありませんでした。
そしてそうであれば、北畠信雄、伊勢北畠氏の未来もまた違ったものとなっていたでしょう……。
1582 北畠信雄と織田諸将の動き
本能寺の変が起こった時、信雄は松ヶ島城にいました。変を知るや信雄や家臣は「まことか、いつハりか」と狼狽して事実かどうか疑いましたが、六月三日には伊賀にいた家臣たちが伊勢へと逃れ始めて来たため、現実を受け入れざるを得なくなります。
信雄はただちに軍勢を集めて鈴鹿郡まで進軍しましたが、明智勢の動きは早く、六月五日には近江国にまで進出して安土城へと入っていました。
この時、蒲生賢秀・氏郷父子が信長への忠義から安土城にいた織田親族らを迎えいれて日野城で籠城し明智勢に対抗していました。蒲生父子は北畠信雄に人質を出して援軍を要請。信雄もこれに応えて近江国土山まで兵を進めています(『勢州軍記』)。
北畠・蒲生勢と明智勢が近江で激突する可能性もありましたが、そうはなりませんでした。
六月七日に羽柴秀吉が姫路城まで到達したことで、光秀は急遽安土城を発して京へ戻ってしまったのです。
そして六月十三日、織田信孝を大将とする織田勢と明智光秀の軍勢が山城国の山崎で激突。戦いは明智勢が敗退し、光秀は逃亡中に討ち取られました。十五日には坂本城が陥落しています。
まだ光秀が敗れたことを知らない信雄は十三日に安土城を攻めるべく兵を進めましたが、既に明智勢は退却しており天主などは明智弥平次(秀満)が火を放ったために焼け落ちてしまっていました(『寛永譜』)。(近年は土民による失火説の方が強そうですが)。
光秀を破った信孝らの軍勢は近江、美濃まで進んで明智方勢力を退け両国を平定。そして織田の諸将はそのまま尾張国清須城へと入りました。北畠信雄は明智勢の去った安土城を接収し、その後は諸将と同様に清須へと赴いています。
1582 伊州蜂起
本能寺の変の直後、伊賀で一揆の蜂起が起こりました。
前年の第二次天正伊賀の乱を恨みに思った伊賀の反織田勢力が仁木城を包囲。伊賀国の織田勢力は北畠勢が土山まで進出してきたことから信雄を頼って援軍を要請しています。
光秀が京へと向かった翌日の六月九日、信雄は沢源六郎、秋山右近将監、芳野宮内少輔ら宇陀勢と本田左京亮(国司家重臣)、天野佐左衛門尉(尾張出身家臣)を鎮圧のために先陣として伊賀国へと派遣しました。北畠軍の侍大将らが国司家時代からの北畠家臣と尾張出身家臣で構成されています。信雄時代の北畠氏の特徴ですね。
初戦では本田左京亮の家老森八郎左衛門尉が伊賀勢と戦い討死。光秀が討たれた後も戦いは続き、六月下旬には北畠勢が森田浄雲の一宮城を攻撃。本田左京亮らが塀に登って城内に攻め込み、浄雲を討ち取っています。また滝川雄利の軍勢も音羽城を攻めて敵を多くを討ち取るなど、北畠勢が反織田勢力の一揆を鎮圧させました(『勢州軍記』)。
北畠信雄は信長横死後の対応が優柔不断であったと評価されることもありますが、軍勢を近江国まで進軍させた段階では伊賀での一揆にも対応しており、明智方に本格的な攻勢を実施することは難しい状況でした。優柔不断で攻勢に出れなかったわけではありません。
織田信孝は摂津衆や羽柴秀吉と連携することで山崎で光秀を討つことができました。しかし信雄には六月十三日段階で周囲に連携できる織田方の大きな勢力は存在せず、光秀に兵力で劣るであろう信雄が単独で戦いを挑むのは厳しいものがあります。
近場の方面軍は信忠軍団ですが、主力の河尻秀隆は甲斐国、森長可や毛利長秀は信濃国と重臣らは旧武田領国に赴任しており、同じ伊勢衆の滝川一益も上野国、弟信孝も摂津にいるため、六月三日から十三日の間では信雄が連携可能な勢力がまったくいないのです。
柴田勝家は六月九日に越前国北庄城まで帰国していますが、なかなか近江へは進出できないでいました。徳川家康は変が起こった時には堺におり、慌てて近江、伊勢を経由して三河へ帰国しています。(大和国通過説もある)。とても数日で信雄と合流など出来ようはずがありません
帰国後の家康は六月十四日には徳川勢を率いて尾張国鳴海まで進出してきていますから、もしも秀吉の大返しがもう少し遅れていたら、北畠信雄、徳川家康、柴田勝家らが連携して近江方面から光秀を攻めていた可能性もあったのかもしれませんね。
(でもそうすると天正壬午の乱での徳川の対応が遅れてしまったかも?)

1582 山崎の戦いに参加した北畠旧臣
あまり知られていませんが、北畠旧臣らが明智光秀の軍勢に加わり山崎の戦いで討死したと伝わります。『北畠御所討死法名』には「天正十年六月十三日明智光秀ト一所ニ討死」とされる武士の名前が十名記載されています(ただ信憑性が微妙な史料ではあります)
大宮九郎右衛門尉光成、松永左兵衛尉秀次、大島勘蔵頼通、畠山小助高義、大宮多気丸吉守、芝山小次郎秀時、家城紋覚頼高、鈴木久右衛門尉家重、桑原伊豆守森信、稲生覚内時秀の十名です。
大宮、芝山は三瀬から逃れた二人ですね。具親がいた備後鞆の浦から短期間で京都へ辿り着けるとは思えないので、おそらく彼らだけが何処か(伊賀?)に潜伏しており、本能寺の変を好機と捉えて加勢したのではないでしょうか。乗るしかねぇこのビッグウェーヴに!
天正九年に死去したとされる鳥屋尾石見守満栄も子息へと「汝主君の為に信長に一太刀うらみよ、我死すとも汝が守神とならん」と言い残していたといわれます(『伊勢国司記略』)。発言の真偽は不明ですが、事実なら彼も最期まで忠義を全うしたようです。
1582 伊賀への対応
天正十年(1582)七月、信雄は滝川雄利、秋山右近将監を大将とする軍勢を伊賀国の滝野城へと派遣しました。
滝川らが加勢を求めたため小川新九郎が清須から出陣して滝野城へと向かっています。小川は奮戦し敵を破ったことで信雄より感状を賜ったようです。なお小川は九月には宮田城攻め、十月には嶋の原攻めで功を上げ、十一月にも雨乞城攻めからの撤退で殿軍を田丸中務大輔と共に務めています。大活躍。
本能寺の変の直後に伊賀勢が蜂起した話は『勢州軍記』がだいたいの出典ですが、変の翌日に北畠家臣が伊賀から逃れてきた事や、その後に伊賀へ出兵したことは当事者である小川新九郎の覚書にもあるので概ね事実なのではないかと思います。
1582 清須会議
天正十年(1582)六月二十七日。尾張国清須城で織田氏重臣らが織田氏の今後を決める談合を行いました。談合のメンバーは「羽柴秀吉」「柴田勝家」「丹羽長秀」「池田恒興」の四名で、談合の内容は主に「今後の政権運営方針」「所領の配分」の二つでした。
通説では織田家督を信雄とするか信孝とするかで揉め、柴田勝家が信孝を推したが羽柴秀吉が丹羽や池田を味方につけ信忠嫡子の三法師を推挙して織田家中の主導権を握るようになっていったとされています。
しかし現実にはそんなことはなく、織田家督は「三法師」で皆が最初から同意していました。そもそも清須城にわざわざ参集したのは、三法師が清須城にいたからであったと考えられていますからね。
1582 名代争い
家督争いはありませんでしたが、信雄と信孝の諍いは実際にこの清須会議で発生しています。それは「家督」ではなく、その「名代」の地位を巡るものでした。つまり幼少の三法師(三歳)の代行者に誰がなるのかで信雄・信孝兄弟が揉めてしまっていたのですね。
北畠信雄は信長生前から信忠の同母弟ということで信孝ら一門よりも上位として扱われています。三法師の直接の叔父にもあたりますし、血縁の濃さ、格では信雄が名代となるのが当然であり、信雄も当然それを望みました。
しかし信孝は明智光秀討伐の大将であり、信長の敵討ちという面では抜群の功績があります。そのため一門内での立場向上を求めて、やはり信孝も名代の地位を望みます。
三法師と血統を同じくする信雄を名代とすれば、嫡流ということで家督を継ぐ三法師の正統性がより維持されますが、しかしそうすると弔い合戦の功労者でるある信孝の功績が低いものとして扱われてしまう。それぞれにそれぞれの立場があり、両者はなかなか妥協できないできないでいました。
そのため四名の重臣らは話し合った末に「これもう名代は置かんでええやろ…」となり、名代は設置せずに四名の重臣に三法師傅役の堀秀政を加えた重臣五人の合議で織田政権を運営すると決定し、これを信雄と信孝に同意させました。
織田信長の子息を政権運営から外すことは通常ではありえないことですが、宿老たちは両人のどちらかに権力を集中して付与することを危ぶんだようです。天下をまとめる織田政権を維持するため仕方のない措置でした。(柴裕之『清須会議―秀吉天下獲りへの調略戦―』)
1582 所領分配
明智光秀、織田信長、信忠らが死んだことで彼らの担当地域は領主不在となってしまいました。この清須会議ではその所領を各重臣らに分配しています。
北畠信雄は尾張国を得ています。信孝には美濃が与えられていて、濃尾両国が織田家督であった信忠の統治する織田氏本国であったことから、織田一門の上位二人に分割して与えられたようです。
これで北畠氏は尾張国と南伊勢五郡、大和国宇陀郡、伊賀三郡(と志摩国?)を領有することになります。何万石あったんでしょう?百万石くらいあったんでしょうか?
1582 伊勢・志摩・紀伊の国境変更
天正十年に伊勢・志摩・紀伊の国境線が変更されました。
紀伊国新宮の堀内氏善が勢力を志摩国尾鷲方面にまで伸長させており、この時期の北畠領、堀内領の勢力圏がそのまま国境として定められたようです(九鬼領もかな?)。
どういう手続きで国境を変更したのかよくわかりませんが、前年に織田信長が堀内氏善に「紀州無漏郡(牟褸郡)境目限相賀為神領」と送っているので、もしかすると信長が死ぬ前に決めていたのかもしれませんね。
まぁとにかく志摩国英虞郡はこの時期に三つに分割されたようです。伊勢・紀州国境は荷坂峠とし、伊勢・志摩の国境は浜島とされ、現在一般的に認識されている志摩国の国境線となりました。結果として志摩国は大きく面積が減少しています。
(水田義一「紀伊半島南端の国境変遷と画定」)
1582 清須城へ居城を移す
天正十年(1582)七月までに信雄は清須城へと移りました。
それまでの居城であった伊勢の松ヶ島城には津川義冬が置かれ南勢奉行として支配を担当することとなっています。義冬の妻は北畠具教の娘なので信雄とは相婿・義兄弟になります。具教粛清からまだ六年。なおも北畠嫡流(国司家)の血縁者にあることが、南勢支配の正統性を担保していたのではないかとも考えられています。
清須に移った信雄は兄信忠の家臣だった者たちも召し抱え、北畠家中は旧織田家臣、北畠家臣、旧信忠家臣らで構成されるようになっています。
1582 信雄の織田復姓と大名北畠氏の消滅
この年、北畠信雄は織田姓へと復姓しました。
詳細な時期は不明ですが、清須へ移り織田氏代々の本拠である尾張国の支配へ乗り出した七月なのではないかとみられています。ただ足利義昭が九月に出した御内書では「北畠中将」となっていることから、復姓は翌年の正月頃ではないかという説もあります。はっきりとわかる史料はなかったはずです。
ともあれ、この復姓によって紆余曲折あれど二百年以上に渡って長らく続いてきた「大名としての伊勢北畠氏」は突然、消滅しました。あまりにもあっけない。嘘でしょ……。
……北畠氏が消滅したので、別にここで書くのやめてもいいんですが、まだ一応北畠関係の出来事が残っているので書いていきます。そう、かつて信雄に反攻した具教弟の「北畠具親」が国司家再興を目指して再び足掻くのです。
……伊勢国司家の再興と書いてますが、そもそも信雄も具教娘の婿として伊勢国司家を正式に継いでいるので国司家当主なんですけどね。他になんて書いていいかわからないから国司家再興と書いてます。(残党の蜂起?)
1582 信孝と抗争
天正十年(1582)六月の清須会議で決定された織田氏の運営体制は半年も持たずに瓦解。織田家臣たちは信雄vs信孝の両陣営に分かれて争うようになりました。
信雄は暫定的な織田家督となって羽柴秀吉らが支援。信孝には柴田勝家らが味方していて、天正十年(1582)十一月から十二月にかけて信雄&秀吉らによる信孝討伐の戦いが起きています。戦いは柴田勝家が豪雪のため越前を出ることができずに信孝方が敗退し降伏しました。
1582 北畠具親の五箇篠山挙兵
天正十年(1582)の十二月晦日。北畠具親が五箇篠山城で挙兵しました(『勢州軍記』)。
年末年始の弓矢事という迷惑極まりない挙兵です。
信雄が信孝攻めで美濃へと出陣した隙を突こうとしたのかもしれませんが、信孝は早々に降伏したため信雄勢は十二月二十五日にはすでに尾張へと帰国していました(諸説あり。後述)。信孝や柴田と連携を試みていたのかは定かではないものの、いずれにせよ間の悪い挙兵でした。
この具親の国司家再興軍には三瀬御所・中御所・大河内殿・坂内殿・長野殿の牢人に吉野・多武峰・根来・粉河の法師ら三千人余もの兵が集まりました。伊勢国内ではなおも北畠具親、伊勢国司家の再興軍に味方する者たちが多かったことが伺えます。
中心にいたのは国司家旧臣の安保大蔵少輔、岸江大炊助、稲生雅楽助らで、再興軍らは多気郡の五箇篠山城へと籠城しました。
小川新九郎が覚書にこの戦いの事を武功談として書き残しており、戦闘経過を知ることができます。
十二月晦日に挙兵した国司家再興軍は三千の兵を三つに分けました。具親が自ら千人率いて五箇篠山城へ籠城。残り二千は松ヶ島城攻撃へと打って出ます。安保大蔵少輔が率いていたとみられる松ヶ島攻撃部隊は、さらにそこから千五百と五百に分かれ、千五百の軍勢は大河内方面から進み、五百の軍勢は御麻生園方面から進みました。
当時の松ヶ島城は信雄の義兄弟(相婿)津川義冬が預かり南勢支配を担当していました。すぐさま兵を繰り出して早期に勝負を決しようとする小川らに対して、津川は城を出て戦うことには消極的でした。津川としては籠城しつつ信雄の援軍を待ち、兵力の優位を確保してから討伐戦を始めたかったのでしょう。津川の態度に小川はおそらくかなりイラついている。
小川は拙速を尊ぶことの理を説いたものの埒が明かず、わずか百五十の兵を率い単独で勝手に出陣してしまいます。そして小川勢は松ヶ島城へと向かう安保率いる再興軍一千五百人と大河内の龍ヶ鼻で激突し、なんと寡兵の小川勢が安保勢を破って勝利しました。わずか百五十人の手勢で十倍の敵を切り崩した小川は松ヶ島城にいる津川に「早く後詰に来い」と出馬を催促しています。
後退した安保率いる再興軍は六呂木と篠山城のある片野方面を結ぶ「鳥はみ坂(鳥羽見峠)」で信雄方の侵攻を防ごうと戦いますが、またしても敗退。残る櫛田川を最後の防衛ラインとしたものの、ここでも敗れてしまい五箇篠山城へと退却しました。
防衛ラインを突破した信雄方は五箇篠山城へと進軍。この段階になってようやく津川が到着しています。小川が城を見て廻ったところ、城内には二~三百人しかおらず「案の外無勢」だったようです。城には一千人程いたはずですが、逃亡した者が多かったか、あるいはここまでの戦いに加勢して消耗していったのかは不明です。
信雄方は放火や水の手を絶った後、城攻めを開始。城へ肉薄する小川は多くの兵を失いながらも突撃していきます。日置大膳亮、長野左京亮、八田甲斐守らが小川に「ちょっと後退しろ!」と注意しますが、小川は攻勢を止めません。最後には大将である津川義冬までもが諫めに来たという。出典が小川の覚書であるため、自身の武勇を盛って話している可能性もありますけどね。
信雄方は具親に対して和睦(降伏)を勧告しますが、具親は条件として「伊勢半国」を要求。どう考えても無理な要求。信雄方はこれを拒否して再び城攻めとなります。
信雄方は激戦の末に二の丸までを落とし、具親勢も必死に落城は阻止しようと防戦しました。二の丸口では小川が安保大蔵と槍を交え互いに手傷を負っています。
しかしもはや具親方の敗色は濃厚でした。正月二日の夜、ついに具親らは城を捨てて伊賀国へと落ち延びました。活躍著しい小川新九郎には信雄から感状が与えられています。
伊賀国へと逃げ延びた北畠具親は再びの挙兵を目指しますが、滝川雄利の攻勢によって伊賀の拠点も制圧されたようです。
反信雄派が挙兵することはこれ以後ありませんでした。国司家再興という北畠具親の野望はついに絶たれてたです。
■信雄の安土入城について(2024年2月15日追加)
以前は信雄の安土入城は三法師に一ヶ月遅れての天正十一年(1583)正月下旬と考えられてきました。
しかし近年では信雄は新たな織田家督として三法師と共に供奉され安土城に入っていたが、北畠具親の反乱に対応するために領国へ一度下向した上で正月下旬に再び安土城へ入城したのではないかと指摘しています。(西尾大樹「豊臣政権成立期の織田信雄とその家臣-滝川雄利文書の検討を中心に-」)
(この説では史料にある「廿五日清□(洲ヵ)令帰城…」は美濃への出陣のために率いていた信雄直属の軍勢を清須まで帰したものと解釈されている)



1584~ その後の織田信雄、北畠具親
信雄、具親の二人のその後についてざっと書いていきます。
北畠具親は小牧・長久手の戦いでは蒲生氏郷に味方して城を開城させています。ただ徳川家臣の本多忠次にも手紙を送っているので、戦局を見た上で秀吉側に付いたようです。
戦後も大名に復帰することはなく、蒲生氏郷の客将として迎えられ、秀吉からも有爾村に千石の所領を与えられたとされます。そして二年後には亡くなったようです。
信雄は天正十二年(1584)の小牧・長久手の戦いを経て秀吉に従うようになっています。この敗戦で南伊勢は没収されて蒲生氏郷に与えられたました。北畠氏の一族、家臣も多くが南伊勢を離れることになり、南北朝時代以来200年以上にわたって支配した南伊勢がついに北畠氏の手から離れました。ただ信雄が天正十三年(1585)に上洛しているのですが、その時期の『兼見卿記』では「伊勢国司」と書いています。一応まだ北畠家督という扱いだったのでしょうか?
信雄は豊臣政権内で内大臣にまで出世。大納言までしか昇進できない北畠氏を凌駕する地位にまで昇ります。しかし天正十八年(1590)の小田原攻めの際に旧徳川領への移封を断ったことから改易されています。小田原在陣中には既に本国でも噂が流れていたようで、馴染みの尾張や伊勢から離れることを嫌う領国内の反発を抑えきれなかったらしい(柴裕之「織田信雄の改易と出家」)。
翌年には赦免され配流先の下野国から上洛。その後は伊予国道後でしばらく過ごしています。あくまで想像ですが、正妻で北畠具教の娘だった千代御前がこの時期に亡くなったようなので道後で湯治療養していたのかもしれません。二人の間に生まれた嫡男の秀雄は近江大溝を経て越前大野の領主となっていますが、慶長十五年に父に先立って亡くなりました。
そして北畠の名字ですが、受け継いでいく人はいませんでした。
千代御前の産んだ秀雄以外にも信雄の子供には木造具政(北畠晴具次男)の娘が産んだ信良がいましたが。まだ幼かったりそもそも信雄も改易されていたりで名乗らせるタイミングがなかったのかもしれません。弟とはいえ嫡男秀雄のバックアップ要員でもありましたしね。
結局、信雄の子が北畠を名乗ることはなく、慶長十七年(1612)に公家の中院通勝三男が北畠親顕を名乗って北畠を復活させています。その二年前に織田秀雄が亡くなっていることも、もしかしたら関係があるのかもしれません。
ただこの北畠親顕も子が無いまま早くに亡くなってしまい北畠氏は断絶してしまいました。
なんかこう……攻められてガッツリ滅亡したわけでも改易されたわけでもないという、初心者になんとも説明しづらい結末を迎えてしまった伊勢北畠氏。(織田になった後は改易だけど)
まぁでも、そういう儘ならない部分も含めて人間の歴史ですから仕方ないですね。
私は信雄時代も北畠氏のひとつとして捉えてますが、具教や一族の粛清で滅亡としてしまう人もいます。そういう人にとっては天正四年が伊勢北畠氏の滅亡なのかな。
信雄は最近は再評価されてるような気がするので、そのうち書籍とか出ないですかね…?実は結構頑張ってたんですよって感じのが出てくれると嬉しいです。

とりあえずこれでおしまいです。
間違ってても「ごめん」しかできないので信用し過ぎずにね!このブログは雑に掛けられたハシゴみたいなものなので!
雑な作りのムック本とかよりは頑張ろうレベルの感覚で作ってます(ムック本で戦国時代の伊勢北畠氏が特集されたことあるのか知らんけど…)。
主な参考文献
『三重県史』 通史編「中世」
『三重県史』 資料編「近世1」
『伊勢北畠氏と中世都市・多気』
斎藤拙堂『伊勢国司記略』
藤田達生編『伊勢国司北畠氏の研究』
小川雄「織田権力と北畠信雄」
柴裕之『清須会議―秀吉天下獲りへの調略戦―』
柴裕之編『織田氏一門』
柴裕之「織田信雄の改易と出家」
和田裕弘『織田信長の家臣団』
和田裕弘『織田信忠』
豊田祥三『九鬼嘉隆と九鬼水軍』
水田義一「紀伊半島南端の国境変遷と画定」
……など。
詳しくは参考文献リストや史料リストをどうぞ
https://dainagonnokura.hatenablog.jp/entry/2023/05/01/221137
https://dainagonnokura.hatenablog.jp/entry/2023/05/01/220822